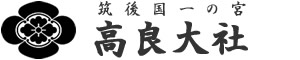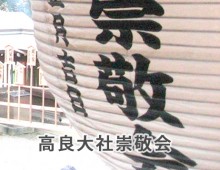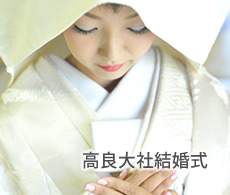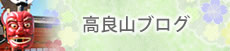高良大社歴史年表

|
時代 |
西暦 |
年号 |
郷土の歴史 |
日本の歴史 |
|
弥 |
前 100
|
紅桃林遺跡(住居跡) 安国寺遺跡(祭祀址)「山川町」、赤坂遺跡 |
||
|
82 |
景行12 |
景行天皇、高羅(高良)の行宮に国内を遊覧し、御井の大川(筑後川)に渡し船を備える |
||
|
200 |
仲哀9 |
神功皇后、天皇と共に筑紫に幸し、高良山に御滞在(安在地・朝妻) 次いで、朝鮮半島に出兵、高良の神、神功皇后を援け給うと伝える |
239 邪馬台国女王卑弥呼。魏に遣使、金印を受ける |
|
|
古 |
300 |
祇園山古墳「御井町」 |
||
|
367 |
仁徳55 |
高良の神(玉垂命)、高良山に御鎮座 |
391 倭軍、百済新羅を攻め、高句麗と交戦 |
|
|
400 |
履中元 |
高良山に社殿を創建し、玉垂宮と称する。 ≪鏡山系譜≫ |
||
|
527 |
継体21 |
筑紫国造磐井、大和朝廷側の近江毛野臣の任那救援軍を阻止 |
527 磐井の乱起る |
|
|
528 |
〃 22 |
物部麁鹿火、筑紫国造磐井を筑紫御井郡に討つ。 |
538 仏教伝来 |
|
|
飛 |
645
|
大化元
|
筑後国府設置。 この頃、筑後川中流域に条里制が施行される |
604 十七条憲法制定 |
|
673 |
天武2 |
仏教高良山に入り、高良の神・仏教帰依の託宣を下す。 |
672 壬申の乱起きる |
|
|
677 |
天武白鳳6 |
隆慶上人・神宮寺高隆寺を創建する≪隆慶伝≫ | ||
|
678 |
〃 7 |
筑紫国大地震 |
||
|
695 |
持統9 |
筑紫国が筑前・筑後に分かれ、筑後国府設置される |
||
|
奈 |
713 |
和銅6 |
従五位下道君首名、筑後国司となる |
|
|
767 |
神護景雲元 |
勅命により大祭礼(神幸祭)が開始される |
||
|
平 |
795 |
延暦14 |
高良神が初めて従五位下の神階を授けられる |
|
|
818 |
弘仁9 |
高良玉垂命神、名神となる |
||
|
840 |
承和7 |
高良玉垂神に従五位上が授けられる |
||
|
855 |
斉衡2 |
高良玉垂名神に位田四町が加えられる |
||
|
869 |
貞観11 |
高良玉垂命に従一位、豊比咩神に正四位が授けられる |
||
|
897 |
寛平9 |
高良玉垂命に正一位、豊比咩神に正四位上が授けられる |
||
|
901 |
延喜元 |
菅原道真、高良山に参詣すると伝える(袴着天神) |
901 菅原道真を太宰府に左遷 |
|
|
927 |
延長5 |
高良玉垂命神社、豊比咩神社名神大社に列する |
||
|
944 |
天慶7 |
筑後守吉志公忠「神名帳」注進、玖留見(くるみ)神初見 |
||
|
949 |
天暦3 |
高良山座主制始まる。高良山十二世叡竿初代座主となる |
||
|
1017 |
寛仁元 |
高良社、香椎、宗像、宇佐と共に一代一度の奉幣にあずかる |
||
|
1085 |
応徳2 |
高良宮が焼亡する |
||
|
1137 |
保延3 |
太宰府高良宮神宮寺高隆寺の大釜鳴動を言上する |
||
|
鎌 |
1201 |
建仁元 |
国司代三善某ら「高良宮造営所課荘々田数注文案」を上申する |
1192 源頼朝、鎌倉幕府を開く |
|
1267 |
文永4 |
蒙古襲来に当たって勅使参向、座主に綸旨を賜う |
1232 貞永式目制定 |
|
|
1268 |
〃 5 |
高良山座主良覚、蒙古調伏の読経をする |
1274 蒙古軍筑前に上陸(文永の役) |
|
|
1274
|
〃 11
|
神代良忠、筑後川に浮橋を架して肥薩隅の軍を渡し北条時宗から感状を受ける 菊池武敏高良山に陣する。進んで太宰府に少弐貞経を攻める |
1281 蒙古・高麗軍再び襲来(弘安の役) |
|
|
1311 |
応長元 |
伏見上皇、高良社造営の院宣を下す |
1334 建武の中興 この頃倭寇横行 |
|
|
南 |
1336 |
延元元 |
菊池武重、大友氏時と高良山に戦う |
|
|
1338 |
〃3 |
一色範氏、菊池討伐のため高良山に陣する |
||
| 1348 |
正平3 |
征西将軍宮懐良親王、高良下宮社に戦勝を祈願して、法華経普門品を書写して玉垂宮に奉納する。谷山城落城 |
1342 征西将軍宮懐良親王薩摩に到着 |
|
|
1353 |
〃8 |
懐良親王、高良山在陣、草野永幸宮方となり、肥前・千栗・船隈の探題一色軍と合戦。筑前針摺原に進発 |
||
|
1359
|
〃14 |
宮方軍、高良山・柳坂・耳納に陣し、筑後川を渡り、大友・少弐(幕府方)の軍と大原で合戦 |
||
|
菊池武光、懐良親王を高良山に奉じ、大友・少弐の幕府軍と決戦(筑後川の戦い) |
||||
|
1372 |
文中元 |
宮方軍、太宰府を失い、親王・菊池武光高良山に征西府を移す |
||
| 1375 |
応安8 |
高良山座主墓中最古の墓石建つ |
||
|
1377 |
天授3 |
懐良親王、高良下宮に願文を納め、九州平定と南朝の衰運恢復を祈る |
||
|
戦 |
1559 |
永禄2 |
大友義鎮、高良山を本陣として筑後を平定 |
|
|
1564 |
〃7 |
大友宗麟、筑後平定のため高良山に出陣 |
||
|
1565 |
〃8 |
原田親種、高良山に籠城し、大友義艦これを攻める |
||
|
1569 |
〃12 |
宗麟、龍造寺討伐のため高良山に出陣。吉見岳に陣する |
||
|
安 |
1573 |
天正元 |
この頃、高良山座主良寛、弟麟圭を笹山(久留米)城主とする |
1573 室町幕府滅亡 |
|
1580 |
〃8 |
龍造寺隆信、筑後に入り、久留米城・高良山を攻め良寛を降ろす |
||
|
1586
|
〃14
|
島津勢高良山を攻略し、仏閣、社家、民屋、悉く焼亡する。大友宗麟、秀吉に救援を求める |
||
|
1587 |
〃15 |
秀吉、島津討伐の途中「吉見が岳」に在陣、神領を没収する。のち千石を神領として寄進。肥筑諸侯の伺侯を受ける。草野家清、参見せず。 同年、筑後に五大名配置、久留米の毛利秀包入城 |
||
|
1591 |
〃19 |
久留米城主毛利(小早川)秀包、座主麟主を誘殺して神領を奪う |
||
|
1596 |
慶長元 |
秀包、麟圭の子秀虎丸座主とし神領を返納する |
||
|
1601 |
〃6 |
田中吉政、三河国岡崎より筑後国主に転じ、柳川に居城 |
1600 関ヶ原の戦い |
|
|
江 |
1620 |
元和6 |
有馬豊氏、丹波福知山より久留米入城 |
1635 参勤交代制度定められる |
|
1650 |
慶安3 |
この頃、山川村の花火「動乱蜂」始まる |
1637 島原の乱 |
|
|
1652 |
承応元 |
高良山に大猷院(徳川家光)廟を建てる。御井町広手参道石造大鳥居竣功 |
||
|
1654 |
〃3 |
第2代藩主有馬忠頼、石造大鳥居を寄進する |
||
|
1660
|
万治3
|
第3代藩主有馬頼利、高良玉垂宮本殿を造営寄進 翌年、五重塔建つ |
||
|
1669 |
寛文9 |
座主寂源、有馬頼元に請うて大祭礼を復活する |
||
|
1670 |
〃10 |
下宮社、祇園社。高牟礼明神朝妻七社等再興される |
||
|
1680 |
延宝8 |
高良山に愛宕神社建つ。331年目御井郡隈山愛宕祠高良山へ遷座 |
||
|
1715 |
正徳5 |
高良神社三年一祭の神事下命 |
||
|
1717 |
享保2 |
十月玉垂宮神幸祭を再興する |
||
|
1748 |
寛延元 |
竹野郡上村庄屋伐木の過料として高良山への並木杉千本を植える(千本杉) |
||
|
1771 |
明和8 |
座主寂信京都伏見から大学稲荷を勧請する |
||
|
1772 |
安永元 |
放生池、御手洗橋(木造)出来る |
||
|
1774 |
〃3 |
琴平神社鎮祭 |
||
|
1777 |
〃6 |
第七代藩主有馬頼徸、中門、透塀を造営寄進する |
||
|
1789 |
寛政元 |
座主伝雄「高良玉垂宮略縁起」を著す |
||
|
1792 |
〃4 |
「千四百年御神忌」行われる。仁王敬一千部を真読 十二月三潴大地震、津波。上妻より二~三千人の人々高良山に登る |
||
|
1797 |
〃9 |
厨寂春、平家物語(重文指定)十二冊を奉納 |
||
|
1803 |
享和3 |
御手洗橋石造りになる |
||
|
1806 |
文化3 |
味水御井神社再建 |
||
|
1812 |
〃9 |
十月、伊能忠敬測量のため府中に来る |
||
|
1839 |
天保10 |
高良山本坂石段百三十段完成 |
1833 天保の大飢饉 |
|
|
1842 |
〃13 |
千四百五十年大祭行われる |
||
|
1845 |
弘化2 |
高良山玉替(金銀)の神事始まる |
||
|
1855 |
安政2 |
下宮社改築 |
||
|
1864 |
元治元 |
真木和泉守、天王山で自刃 |
||
|
1867 |
慶応3 |
この頃、高良山度々鳴動する |
||
|
明 |
1868 |
明治元 |
神仏分離令出る。有志策動の風聞により、高良山及び城下を固める |
1868 戊辰戦争。五箇条の御誓文 |
|
1869 |
〃2 |
旗崎招魂所(山川招魂社)建つ 全山に廃仏毀釈行われ座主廃止される。知藩事有馬頼咸、居を座主跡に定める(高良山御殿)。山中の子院は藩兵屯所となる |
||
|
1871 |
〃4 |
高良玉垂宮を高良神社と改称、国幣中社に列せられる |
1871 廃藩置県 |
|
|
1874 |
〃7 |
久留米城廃城 |
1874 佐賀の乱 |
|
|
1876 |
〃9 |
御井町制をしく。清水小学校を御井小学校と改称 |
||
|
1878 |
〃11 |
高良山下に御井寺(座主院の後身)再興される。御井郡役所設置 |
1877 西南戦争 |
|
|
1890 |
〃23 |
一千五百年遠期大祭行われる。教育勅語発布 |
1894 日清戦争起きる |
|
|
1910 |
〃43 |
神幸祭、久留米市内巡幸始まる(日吉神社、篠山神社)。 |
1904 日露戦争起きる |
|
|
大 |
1915 |
大正4 |
高良神社、国幣大社御昇格 |
1923 関東大震災 |
|
昭 |
1932 |
昭和7 |
高良神社参道自動車道路着工 |
1931 満州事変起きる |
|
1941 |
〃16 |
一千五百五十年御神期大祭行われ、日吉神社、篠山神社に御神幸九州最大の祭と評される |
1937 日中戦争起きる 1941 大東亜戦争起きる |
|
|
1943 |
〃18 |
三井郡御井町、久留米市に合併される |
1945 久留米大空襲 |
|
|
1947 |
〃22 |
社格廃止により、高良神社を高良大社と改称 |
||
|
1951 |
〃26 |
神幸祭、神輿旭屋デパートに至る |
||
|
1961 |
〃36 |
高良山自動車道路(高良大社まで)整備なる |
||
|
1965 |
〃40 |
高良会館落成 |
1964 東京オリンピック大会開催 |
|
|
1969 |
〃44 |
祇園山古墳発掘調査始まる。耳納スカイライン全面開通 |
||
|
1972 |
〃47 |
高良大社社殿、石造大鳥居、重要文化財の指定受ける |
||
|
1973 |
〃48 |
社殿の解体修理始まる |
||
|
1977 |
〃52 |
御井風流復活さる |
||
|
平 |
1991 |
平成3 |
一千六百年御神期大祭 神輿大修理を行う |
|
|
1992 |
〃4 |
一千六百年御神期大祭 神幸祭復活 |
||
|
2004 |
〃16 |
高良大社中門透塀保存修復 |
||
|
2005 |
〃17 |
防災設備施設設置、祓殿増改築完成 |
||
|
2006 |
〃18 |
末社等屋根葺替工事始まる |
||
|
2008 |
〃20 |
高良大社崇敬会設立される |
||
|
2012 |
〃24 |
神幸祭斎行(以後五年に一度斎行予定) |
「 」印 田中幸夫氏「高良山年表」